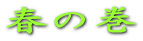 |
|
|
 |
|
 |
| 庄内の山人たち |
|
ぶなの森の案内人 渡 辺 幸 任 |
|
 |
|
 |
| ● |
険しい岩山を這い上がって、
やっとゼンマイ場に着く |
|
|
| ● |
崖に群生するゼンマイ。
この日は20キロのゼンマイを背負って崖を下った |
|
|
 |
 |
 |
| ● |
命綱を使ってのゼンマイ採り。
ゼンマイは雄しべととも半分残す |
|
|
ボートを使ってゼンマイ場に向かう山人たち |
|
 |
| ● |
ゼンマイ場にはウド、コゴメ、タラノメ、コシアブラなどの山菜が豊富であるが、
目指す本命はゼンマイである |
|
|
|
 |
|
 |
まだ綿毛が残るゼンマイを
上から15㎝で採取する山人 |
|
太さ9ミリ、長さ16メートルのロープを固定する
アメリカ製登高器
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| ● |
ゼンマイの手揉み名人・宿坊田村坊の田村茂夫さん |
|
|

筵に干されたゼンマイと
干し上がったゼンマイ(手前) |

干し上がったゼンマイ20キロ |
 |
| ● 印の写真をクリックすると大きい写真を見ることができます |
干し上がったゼンマイ20キロ |
|
 |
|
 |
| ● |
車道に出たマムシ。
マムシは必ず捕る。頭を棒で軽く叩いて
抵抗しなくなったら腹の下に棒を入れ
透明の厚いビニール袋に入れる。 |
|
|
マムシの入ったビニール袋と
一升瓶の口を合わせて縛った後、
瓶に布を被せると
マムシは自ら瓶に入る。
|
|
| |
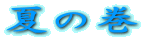
|
|
|

湯殿山側のタケノコ山の入り口に立つ夫婦
|
 |

湯殿山側のオオッピラと呼ばれるタケノコ山
彼方に見える山肌の雪渓は、
月山側のタケノコ山 |
|
道沿いの可憐なイワカガミ |
|
|
 |
 |
 |
|
|
月山の秘境・雨告山(西補陀落)が
間近に見える |
さらに進むとオオダイラと呼ばれる
月山筍の採り場がある。
左奥の山々は月山山頂 |
|
 |
|
 |
チシマザサの笹藪に分け入り、
枯れ葉を押し上げるように生えている
月山筍を探す |
|
| ● |
親竹の根元から生え4本の月山筍。
根曲がり竹ともいう。
だいたいは親竹の根元に1~2本であるが、
時には4~5本の場合もある |
|
|
 |
 |
 |
およそ40キロの月山筍を背負った
西川町の山人 |
およそ50キロの月山筍を背負った
西川町の山人
|
およそ40キロの月山筍を背負って帰る
田麦俣の山人たち |
|
| ● 印の写真をクリックすると大きい写真を見ることができます |
 |
|
 |
| ● |
20キロの月山筍を背負い
月山八合目のタケノコ山の入り口に立つ |
|
|
月山筍の採り場は2メートルを超えるチシマザサに覆われ
周りは見えなくなる。
採り場の確認のために笹の上に赤い袋を縛るときもある
|
|
 |
|
 |
親竹の根元の5本の月山筍
喜びの瞬間である |
|
| ● |
月山筍を手にすると根元がピンクで実に美しい
美術品という人もいる。 |
|
|
 |
 |
 |
| ● |
6月初旬、大雪渓で
20キロの月山筍を背負う
天候が荒れると帰る方向を見失う |
|
40キロの月山筍をバンドリで背負う
山人
|
40キロの月山筍をバンドリで背負う
山人たち |
|
 |
|
 |
40キロの月山筍を背負い
タケノコ山の入り口に到達 |
|
月山筍採り50年の大ベテラン
40キロの月山筍を背負う |
|
 |
|
 |
| ● |
牧場を営む友人のバイクを借り
月山筍を背負い帰還 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| ● |
月山頂上小屋に泊まった翌朝、
朝日に冴えるクロユリ |
|
|
月山筍の調理を始める
月山頂上小屋の芳賀竹志さん
|
|

夕食の月山筍、海老、アザミの天ぷら。
天然マイタケと高野豆腐で
ゴボウと人参を包んだ煮物、
ゼンマイとコシアブラの白和え。
前菜に前年秋の山ブドウ酒
● |

特注の焼いた月山筍
|
 |
|
|
月山筍の味噌汁はとても美味で
お椀に3本の月山筍が付く |
|
 |
| ● |
宿坊田村坊の精進料理。
左側に月山筍の天ぷら、ワラビのお浸し。
右側に月山筍と厚揚げの煮物、ゼンマイの煮物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
| |
| ● 印の写真をクリックすると大きい写真を見ることができます |

|
 |
|
 |
エゾハリタケ、ふたつ合わせて21キロ
塩漬けにして1年、さらに味噌と麹に1年漬けると
飴色の漬け物になる。独特の風味で逸品である。 |
|
天然のあけびは味噌と炒めて食べる。
|
|
 |
| 高所のエゾハリタケ採り |
 |
高所のエゾハリタケを
ロープをかけて採取 |
 |
|
 |
| 採取したエゾハリタケ |
|
|
|
|
 |
|
|
| 月山の山ふところの急斜面でマイタケ発見 |
 |
| ● |
月山五合目から望む庄内平野と鳥海山。
手前の池は龍神伝説の狩籠池。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| ● |
山ブドウも登高器を使って採る。
両手が使えるのでブドウ蔓が痛まない |
|
| ● |
山ブドウの木が10メートルでも
ロープを使って登って採る |
|
収穫した山ブドウ40キロ。
二度に分けて車道まで運ぶ |
|
 |
| 庄内のきのこを代表するナラタケの群生 |
 |
|
 |
|
|
|
ブナの立木に群生するナラタケ。
この周辺で15キロ採取できた。
|
|
| ● 印の写真をクリックすると大きい写真を見ることができます |
 |
| |
9月半ばの早生のナラタケ。
ビニール袋に入れて空気を抜いてリックに入れるとよい。
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
ブナの倒木に群生するブナハリタケ。カノカともいう。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
収穫したカノカ、ナメコ合わせて20キロ。
|
|
|
|
 |
その年のキノコの終わりを告げるアカモタシ。
ヤマドリともいう |
|
 |
|
 |
収穫したヤマドリ(左端)とナメコ、カノカが少し
|
|
晩秋、落葉して山ブドウだけになった。
これは甘くて美味しい。
|
|
|
|
|
|

ブナの実の残渣が詰まった
熊の糞 |
 |
 |
|
|
新雪とナメコの群生、20キロ採取。
近くの笹藪の雪上に熊が潜んだ跡あり
|
|

前年と同じ倒木から採取ナメコ
前年の半分しか採取できず |

| ● |
ナメコに付着する虫を食べにきた
ハコネサンショウウオ。
かわいい生き物である |
|
 |
| きのこご注文ページに |
|
25キロナメコが詰まったリック。
過去最高の採取記録
|
● 印の写真をクリックすると大きい写真を見ることができます |
| ページの先頭に戻る>春の巻に戻る>夏の巻に戻る>秋の巻に戻る |
| |
|
|
| ( 2011年 特別の巻のページは、上記ロゴをクリックして下さい ) |